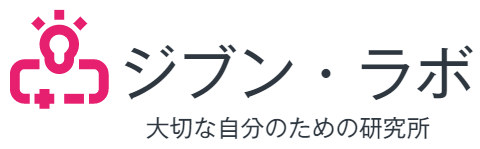REBTが進化する! 新しい用語がもたらす柔軟性と可能性について考えてみた
Rational Emotive Behaviour Therapy(REBT)は、心理支援現場で長年にわたり使用されてきた、科学的根拠に基づく有力なアプローチです。その中核であるABCD理論は、多くのセラピストやクライアントにとって馴染み深いものとなっています。
しかし、時代やクライアントの多様化に伴い、従来の用語が持つニュアンスや解釈の幅が、セラピー現場で一定の課題を生んでいることが議論され始めました。特に、クライアントがセッション中に抱える心理的負担や、セラピストとの関係性への影響が指摘されています。
このような背景を受け、ドライデン氏は著書「Dealing with Emotional Problems Using REBT」の中で、ABCD理論に用いられる用語の変更を提案しました。本ブログでは、この用語変更が持つ意義を検討するとともに、それがどのようにセラピーの実践を変える可能性があるのかを探ります。
Table of Contents
用語変更の詳細
Rational Emotive Behaviour Therapy(REBT)におけるABCD理論は、心理支援現場で広く用いられているアプローチ理論です。しかし、最新の研究と実践の中で、従来の用語が持つニュアンスや解釈の幅が、クライアントとのセラピーにおいて一定の課題を生じさせることがドライデン氏の著書 「Dealing with Emotional Problems Using REBT 」では指摘されています。彼は同著の中で、「Activating Event(出来事)」という言葉は、クライアントにとって「出来事そのもの」を指すのか、「出来事の中で心理的に重要な要素」を指すのか、解釈が曖昧になりやすい側面がある、と指摘します。私自身は「Beliefs(信念)」という用語も、クライアントの価値観や個人的な信条に直結することが多く、それを「不合理」と指摘されると抵抗感を生むケースが少なくないと考えています。
ドライデン氏のDealing with Emotional Problems Using REBTを参考に、従来の用語とドライデン氏の提案する新しい用語の比較を以下の表にまとめました。
次章からその変更意義を皆さんと一緒に考察していきたいと思います。
| 従来の用語 | ドライデン氏 提案の新しい用語 | 変更の意義 |
| Activating Event(出来事) | Adversity(危機) | 事象の曖昧さを排除し、困難な側面に焦点化 |
| Beliefs(信念) | Basic Attitude(基本的態度) | 信念よりも柔軟性を持ち、変更しやすい |
| Rational/Irrational (合理的/非合理的) | Flexible/ Rigid(柔軟/頑な) | 批判的なニュアンスを排除し心理的健康を反映 |
| Disputing(論駁) | Examining(検証) | クライアントとの協力的な姿勢を重視 |
変更点の解説詳細
本章では、ドライデン氏が提案した具体的な用語変更について、その背景や意義を詳細に解説します。これにより、新しい用語がセラピー実践にどのように役立つのかを明らかにします。
Activating Event(出来事)から Adversity(危機)
従来の「Activating Event(出来事)」は、出来事そのものを指すのか、出来事内で感情を引き起こす特定の要素を指すのか解釈が曖昧でした。これに対し、新しい「Adversity(危機)」は、問題の核心に迫る用語として変更することにより以下のメリットが考えられます。
- 焦点の明確化: 単なる事象ではなく、クライアントにとって心理的影響を与える本質的な側面に注意を向けられる。
- 例: 「仕事の失敗」という出来事ではなく、「評価が下がった」という危機的な部分を強調。
- 感情の源泉を特定: 感情反応を引き起こす具体的な要因を特定しやすくなる。
Beliefs(信念)から Basic Attitude(基本的態度)
「Beliefs(信念)」という言葉は、価値観や個人の深い思いに結びつくため、「不合理な信念」と指摘されることでクライアントに抵抗感を与える場合がありました。この点を踏まえ、「Basic Attitude(基本的態度)」への変更が提案されています。変更することにより以下のメリットが考えられます。
- 柔軟性の強調: 「態度」という概念は、変更可能であるというイメージを与え、クライアントが受け入れやすい。
- 例: 「信念を押し通す」という表現に比べ、「態度を変える」は抵抗感が少ない。
- 心理的負担の軽減: 批判的なニュアンスを排除し、クライアントがセッションに前向きに取り組める環境を提供。
Rational/Irrational(合理的/非合理的)から Flexible/ Rigid(柔軟/頑な)
「Rational(合理的)」や「Irrational(非合理的)」という言葉は、批判的な響きを持ち、クライアントの自己否定を引き起こす可能性がありました。これに対して、「Flexible/ Rigid(柔軟/頑な)」は次のようなメリットが考えられます。
- 批判性の排除: 「柔軟」「頑な」という言葉は、態度や選択の改善に焦点を当て、クライアントが受け入れやすい。
- 心理的健康の反映: 極端な態度よりも柔軟性を重視することで、心理的健康を促進。
Disputing(論駁)から Dialectically Examining Attitudes(対話的に態度を検証する)
「Disputing(論駁)」はセラピストとクライアントの対立的なニュアンスを含む可能性がありました。これに対し、「Examining(検証)」は以下のメリットが考えられます。
- 非対立的アプローチ: クライアントと協力しながら態度を検討する姿勢を重視。
- 適用範囲の拡大: 柔軟性や極端さの程度に焦点を当て、より包括的なセッションが可能。
- 例: 「頑なで極端」な態度と「柔軟で非極端」な態度を比較し、どちらが望ましいかをクライアントと共に探る。
これらの用語変更は、クライアントの心理的負担を軽減し、セラピーの柔軟性を向上させることを目的としています。それぞれの変更が持つ実践的な意義を理解し、活用することで、セラピーの効果をさらに高めることが期待されます。
まとめ
本ブログでは、ドライデン氏が提案したREBT(Rational Emotive Behaviour Therapy)の用語変更について、その背景と実践的な意義を解説しました。これらの変更は、クライアントへの心理的負担軽減やセラピーの柔軟性向上に寄与することが期待されています。
新しい用語に変更することで得られる主な利点
新しい用語に変更することで次のような利点が考えられます。
- クライアントへの心理的負担軽減
- 批判的なニュアンスを排除することで、セラピーへの抵抗感を減少。
- 例: 「非合理的な信念」ではなく、「柔軟性の欠如」という表現を使うことで、自己否定感を避ける。
- 批判的なニュアンスを排除することで、セラピーへの抵抗感を減少。
- セラピーの柔軟性向上
- 用語が具体的で明確になり、状況に応じたアプローチが可能。
- 例: 「出来事」よりも「危機」とすることで、感情の源泉に焦点を当てた対応がしやすくなる。
- 用語が具体的で明確になり、状況に応じたアプローチが可能。
- クライアントの主体性を促進
- 新しい用語はクライアントが自己理解を深め、自ら課題に向き合う動機を高める。
- 例: 「態度を検証する」というプロセスが協力的で、自己変革を促す。
- 新しい用語はクライアントが自己理解を深め、自ら課題に向き合う動機を高める。
新しい用語を使う上で留意するべきこと
上記のように新しい用語に変更する上で多くの利点が考えられますが、実際に使う上のでは以下のことに留意する必要があります。
- セッションでの導入時
- 用語変更を説明する際、クライアントの立場に立った言葉を選び、十分の理解を得る
- セッションの効果検証
- クライアントからのフィードバックを元に用語変更後のセッションを評価する。
- 変更が実際のセラピストとクライアントの間の関係にどのような影響を与えたか検証する。
今後の展望
これらの用語変更は、REBTがより多様なクライアントに対応できるツールとなる可能性を秘めています。私自身もこれらの変更を積極的に取り入れ、以下の観点で実践的な効果を検証していきます。
- 心理的負担の低減: クライアントが前向きに課題に取り組む姿勢が見られるか。
- 柔軟性の向上: 多様な状況や背景を持つクライアントに対応できるか。
- クライアントの成長: 自己変革を促進する結果が得られるか。
皆さんも是非新しい用語を実際のセッションに取り入れ、その効果を確かめてみてください。セラピストとクライアントの双方にとって、より良い対話と成長をもたらす第一歩となるはずです。